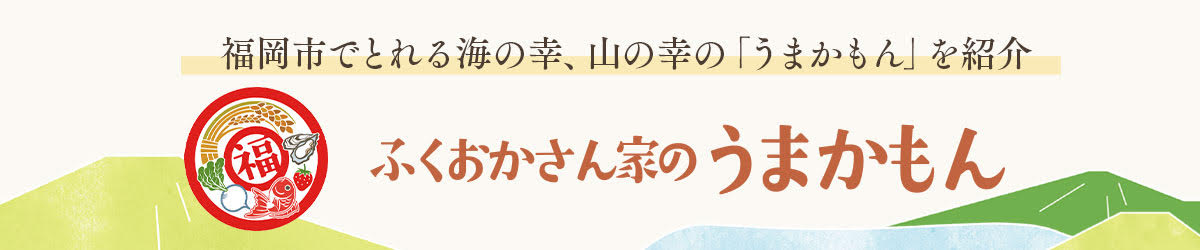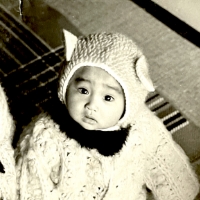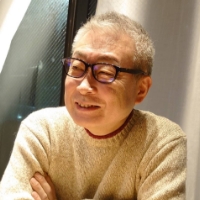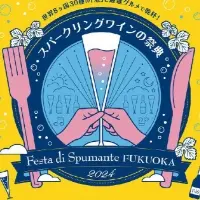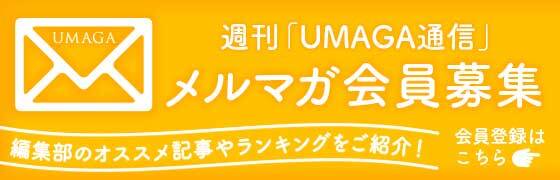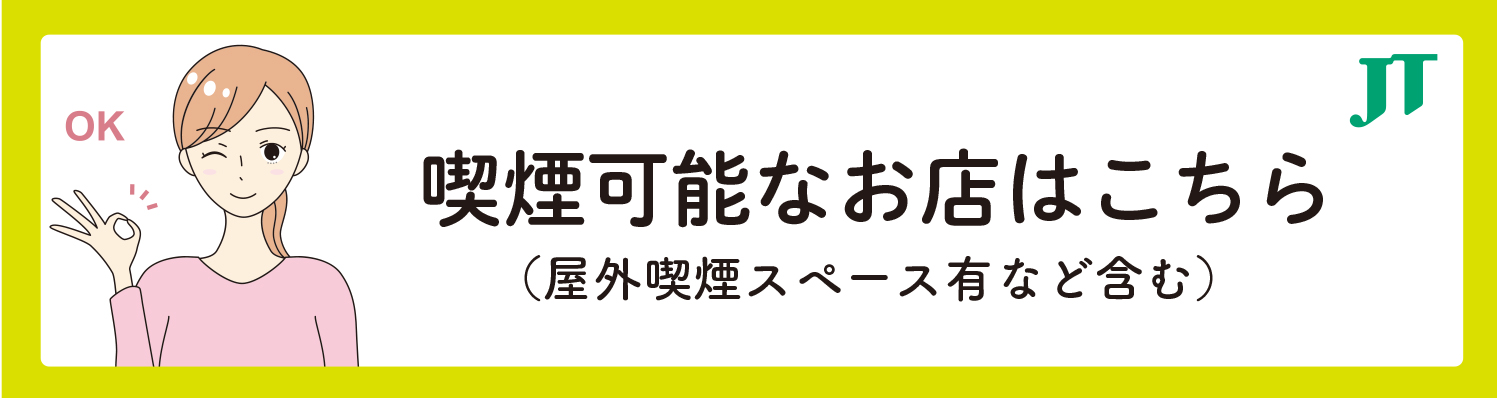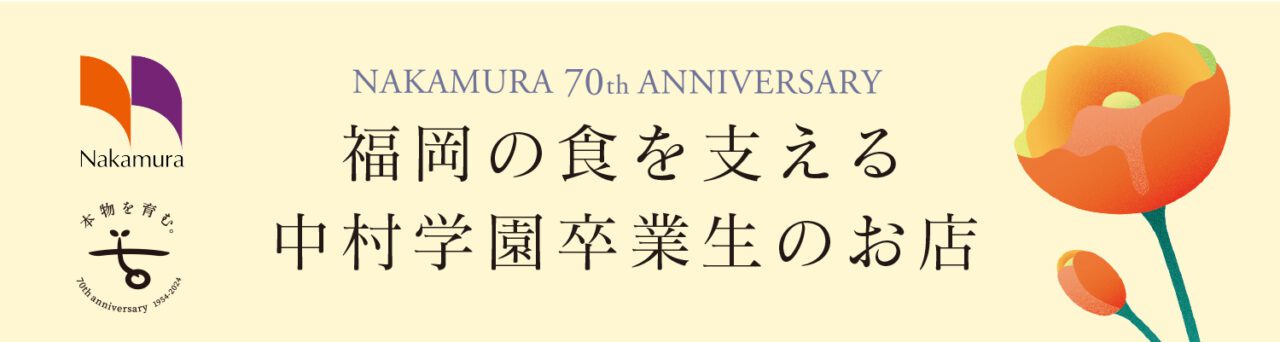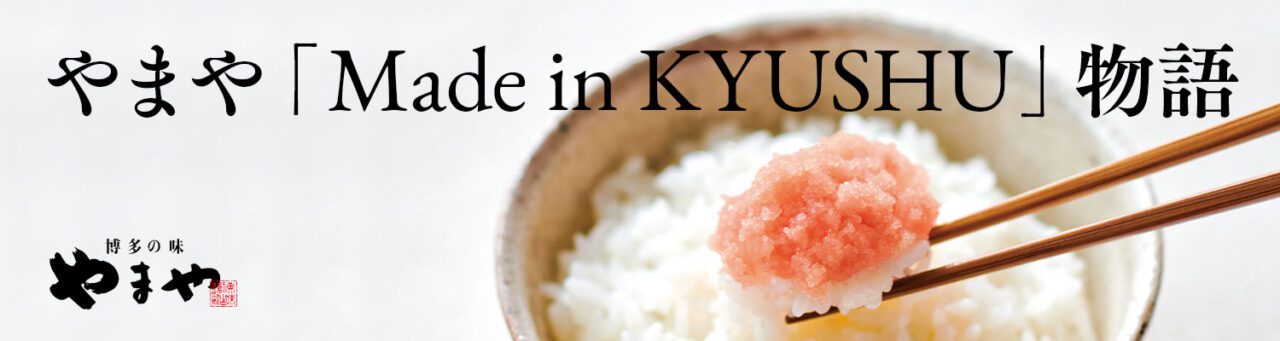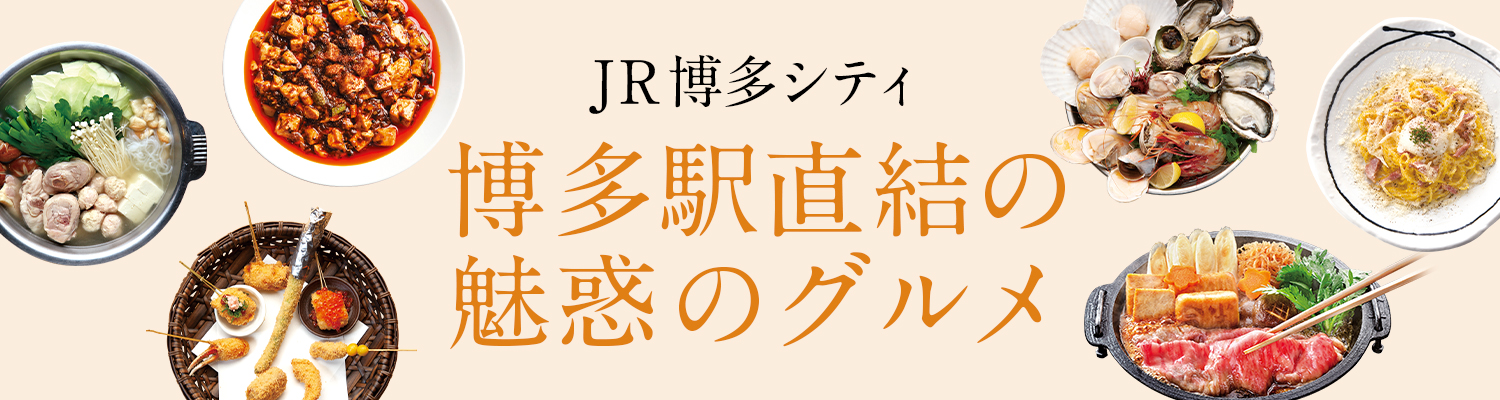焼酎の熱がついに福岡へ!酒屋✕飲食店店主が語る、焼酎の現在地

近年、焼酎の楽しみ方が広がっています。ソーダ割りで香りを楽しむタイプの銘柄が注目され、飲食店での提供も増加中。大阪・東京をはじめ全国の都市ではすでに新しい潮流が広がり、全国誌でも特集が組まれるなど、焼酎が“選ばれる一杯”として定着しつつあります。その波がようやく福岡にも届き始めました。今回は、「いま、焼酎がおもしろい!」をテーマに、酒屋、飲食店、イベント実行委員長の3名の立場から、焼酎を取り巻く現状とこれからを語っていただきました。
いま、焼酎が気になる理由

※写真左から
川瀬 一馬(かわせ・かずま)さん
1976年生まれ。福岡市で人気ビストロ「Yorgo」や「餃子のラスベガス」を営む料理人。ワインを中心に幅広いアルコールを提案しつつ、近年は焼酎の可能性にも注目している。
轟木 渡(とどろき・わたる)さん
1972年生まれ。「とどろき酒店」代表。ナチュラルワイン、日本酒、本格焼酎をバランスよく扱い、「酒屋が選ぶ焼酎大賞」実行委員も務める。
野見山 大翔(のみやま・ひろと)さん
2000年生まれ。「とどろき酒店」スタッフ。ナチュラルワインや日本酒をきっかけに酒の世界に入り、現在は本格焼酎にも熱心に取り組む。2025年7月開催「High焼酎Fukuoka」の実行委員長。
轟木 最初にお二人に伺いたいのですが、焼酎に惹かれたきっかけは何だったのでしょう?
川瀬 僕は約2年前、「小烏」という店で「安田」(鹿児島・国分酒造)を飲んだんですけど、「これ本当に焼酎?」って驚いたんです。香りが素晴らしくて、そこから一気にハマりましたね。
野見山 分かります。僕も最初は焼酎じゃなくて、ナチュラルワインや日本酒、ウイスキーなどを飲んでいました。学生時代は居酒屋でバイトしていて、日本酒をよく飲んでいましたし、同時にウイスキーも好きで。だから焼酎のソーダ割りには抵抗がなかったんです。3年ほど前に「山ねこ」(宮崎・尾鈴山蒸溜所)を買ってみて、「焼酎ってこんなに香るんだ!」って驚き、そこから一気に世界が広がりましたね。
轟木 お二人とも“香り”に驚かれたのですね。私は酒屋の家に生まれ、小さい頃から焼酎はとても身近でしたが、正直、苦手でもありました。20代後半に西酒造(鹿児島)の焼酎を飲んで、「芋でもこんなに飲みやすいものがあるんだ」と気づいたんです。90年代は焼酎ブームまっただ中で、芋焼酎なら何でも売れるという、ある意味“異常な状況”でした。その後ブームは落ち着きましたが、定期的に焼酎の勉強会に参加し、焼酎と向き合い続けてきました。だからこそ、いまこうして“焼酎がおもしろい”と語れる時代になったことを、とても嬉しく感じています。
“酒屋”の視点から見た焼酎の変化


画像はとどろき酒店より提供
轟木 焼酎を取り巻く環境も、この5年ほどで大きく変わってきました。私自身、「酒屋が選ぶ焼酎大賞」の立ち上げから関わっていまして、今年で4回目になります。準備を含めると6年ほど。最初は売上に直結していませんでしたが、最近では徐々に認知されるようになってきました。
野見山 そういえば、先日、ある百貨店のお酒売場を通ったら、「酒屋が選ぶ焼酎大賞受賞」というPOPを見かけましたよ。
川瀬 確かに、ここ数年で「焼酎大賞」や「香り系」という言葉もよく耳にするようになりましたよね。ナチュラルワインやクラフトジンのように、コンセプトがはっきりしていて、飲食店としても扱いやすくなったと感じています。
野見山 僕の周りでも、焼酎にハマる人が増えています。とくに「香り系」や「ソーダ割り」といったコンセプトがあると、伝えやすいんですよね。実際に飲んだ人も「こんなに香るんだ」と驚いてくれるので、そこから興味を持ってもらえるんです。
轟木 その通りですね。焼酎ってもともと“飲み手に寄り添う酒”で、お湯割りや水割りなど、自由な飲み方を前提に造られてきました。けれど、最近は意図を持って設計された焼酎が出てきています。香りを際立たせる酵母や麹の組み合わせ、発酵や蒸留温度を調整して余韻を長くする仕組みなど。たとえば、“ソーダ割りで際立つ”ことを意図して造られた銘柄もあります。こうした設計があるからこそ、香り、余韻、重心といった言葉で語れる時代になってきたと思います。
飲食店から見た焼酎のポテンシャル

画像はとどろき酒店より提供
轟木 川瀬さん、実際にお店で焼酎を提供してみて、反応はいかがですか?
川瀬 「餃子のラスベガス」はまだしも、正直、「Yorgo」では難しいかなって思っていたんですよ。でも、実際にお出ししてみると、ワイン好きなお客様からも「焼酎もアリですね」と言っていただけることも多くて。メニューのドリンク欄に自然に焼酎が並んでいるだけで、「ちょっと試してみようかな」となる。そういうきっかけをつくることが大事だと感じています。
野見山 酒屋の立場からすると、やっぱりソーダ割りは入口としても強いですね。飲み口が軽いですし、食事にも合わせやすいんですよね。
轟木 さっきも話に出ましたけど、やはり香りで新しい世界を見せてくれる銘柄が出てきたことが大きいですね。
川瀬 僕自身も、年齢を重ねるにつれて身体に負担が少ないお酒を選ぶようになりました。焼酎は軽やかで、翌朝も調子がいい。だからこそ、飲食店でも提案の輪を広げていきたいと思っています。
福岡に吹き始めた“焼酎の風”

画像はとどろき酒店より提供
轟木 7月27日に開催されたイベント「High焼酎Fukuoka」についても、少し振り返ってみましょうか。きっかけは川瀬さんだったんですよね。
川瀬 はい。最初は僕が野見山さんに「なんか面白い焼酎ない?」って声をかけたことでした。いくつか持ってきてくれて、そのときにすごく熱く語ってくれて(笑)。そこから、「じゃぁ、イベントやろっか」って流れになったんです。
野見山 そうでしたね。最初は雑談みたいな感じでしたけど、川瀬さんが「面白い」と言ってくれて、すぐに動き出しました。轟木さんと一緒に蔵元に声をかけて、会場は川瀬さんの「Yorgo」と「餃子のラスベガス」を使わせていただいて。福岡・熊本・宮崎・鹿児島の6蔵が集結し、5軒の飲食店がフードを提供してくれることになりました。結果的にアフターパーティまでを含めると延べ200名以上が参加。想像を超える盛り上がりでした。
轟木 福岡でこの規模の焼酎イベントは初めてでしたね。これまでも単独蔵の試飲会などは行われていましたが、複数蔵が一堂に会する場はなかったと思います。東京や大阪では数年前からこうした動きがありましたが、福岡は産地が近すぎて、逆にムーブメントが遅れていたんです。蔵元の皆さんからも「ようやく福岡でこういった会ができた」と喜んでいただきましたし、全国的な波がようやく福岡に届いたことを実感できました。
野見山 ただ反省点も少しあって。今回、来場者は焼酎好きな飲食関係者や、従来の焼酎ファンが多く、年齢層も高めでした。当初は、若い人や焼酎に触れてこなかった人にも来てほしかったんですが、これは今後の課題ですね。
川瀬 とはいえ、焼酎は若い世代にも確実に届き始めていると思いますよ。たとえば、「TRESOL(トレソル)」という店では、「飫肥杉(おびすぎ)」のジャスミンティ割り、通称“オビジャス”がオフィシャルドリンクのような存在になっていて、若い子たちが普通にオーダーしている。「知らずに焼酎を飲んでいる層がいるんだ」と実感しました。また、最近は「再来(サイクル)」という立ち飲みにもよく行くんですが、そこでも若い世代が自然に焼酎を楽しんでいる姿を見るんです。焼酎はこれからも、もっと自然に広がっていくと思いますね。
焼酎の未来を、どう描くか
轟木 さきほどもお話しましたが、いまの焼酎のムーブメントは東京や大阪に比べると福岡はやや遅れて入ってきました。だからこそ、今後の伸びしろは大きいはず。私たち酒屋としては、焼酎を“自由なお酒”としてもっと提案していきたいですね。飲み方も価値観も多様になれば、文化として根づいていくと思います。
川瀬 飲食店としては、焼酎を特別なものではなく、日常の選択肢の一つとして浸透させたいですね。ワインやビールのように、気軽に飲める一杯として提案することで、若い世代にも自然に受け入れられると思っています。焼酎は軽やかで食事に寄り添う酒。だからこそ、福岡という土地で文化として定着させたいですね。
野見山 まずは、「とりあえずビール」ではなく、「とりあえず焼酎ソーダ」という時代になればいいなと思っています。軽やかで飲みやすく、食事にも合わせやすい。そこから、焼酎の未来が広がっていくはずです。だからこそ、店頭やイベントで造り手の思いや飲み方を伝えることに意味があります。これからはもっと、自分と同じ若い世代にもアプローチして、「焼酎って面白い」と気づいてもらえる場をつくっていきたいと思っています。
3人の話を聞いて、焼酎はいま、“再発見”ではなく“新発見”の段階に入っていると感じました。単なる懐かしさではなく、新しい飲み物として受け止められつつあるのです。九州では昔から身近にありすぎて見えづらかった価値も、いま改めて鮮やかに立ち上がってきました。
料理を邪魔しない柔軟さ、スパイス料理との相性の良さ、ガストロノミーとの親和性の高さ――これからの焼酎の可能性を広げてくれることでしょう。
焼酎は、これからが本当に面白く、楽しみな存在になっていくはずです。
類似の記事
- ※この記事は公開時点の情報ですので、その後変更になっている場合があります。
- ※「税別」という記載がない限り、文中の価格は税込です。
- ※掲載している料理は取材時のもので、季節や仕入れにより変更になる場合があります。
- ※OSはオーダーストップの略です。
- ※定休日の記載は、年末年始、お盆、祝日、連休などイレギュラーなものについては記載していません。定休日が祝日と重なる場合は変更になる場合があります。
記事に関する諸注意
- ※この記事は公開時点の情報ですので、その後変更になっている場合があります。
- ※「税別」という記載がない限り、文中の価格は税込です。
- ※掲載している料理は取材時のもので、季節や仕入れにより変更になる場合があります。
- ※OSはオーダーストップの略です。
- ※定休日の記載は、年末年始、お盆、祝日、連休などイレギュラーなものについては記載していません。定休日が祝日と重なる場合は変更になる場合があります。
人気記事ランキング
- 24時間
- 1週間
- 1ヶ月